(本エントリは、私が別の web に 2004年 6月 23日付で掲載していたものを転載後加筆訂正したものです) (this article is an impression of my surprise meet with the great-sounding LP, Firebird / LSO, Dorati, left on Mercury label. and it was originally made public at my another web site on June 23, 2004. English version of this article (probably) will not be available.)
“The Golden Age of Recording” (Michael Gray、嶋 護 翻訳) より:
もっとも完璧なレコードを選ぶコンテストがあったら、この一枚を推しよう。
2002年頃、この一文で始まる記事を某雑誌で初めて読んだ時、「またそんなおおげさな」と思ったものです。
しかし、実際にその盤を聴いてみた時、ぐうの音も出ませんでした。超絶な録音、スリリングな演奏、その両方の素晴らしさに、本当に鳥肌をたてながらスピーカの前で呆然としてしまいました。これはマジでとんでもないレコードでした。うちの現状のオーディオではその半分、いや二割も享受できていないのかもしれませんが。
とにかくこの時期 (1950年代初期から1960年代初期に到るまで) の Mercury レーベルのクラシック録音はもはや超絶の別次元です。
U47 マイクの独特の音色、 顕微鏡で覗きこんでいるかの様なフォーカスと細部の描写、 そして生々しい空気感とすかっと広がる空間イメージ。 演奏抜きですら鳥肌がたつ様な盤が目白押しです (中には失敗作もありますが、その数は他レーベルに比べると驚くほど少ないです)。
David Hall, C.R. Fine, Wilma Cozart, George Piros, John Johnston その他の、黄金のスタッフによる録音にはほぼ外れがありません。 このレーベル全体を見渡してみると、気鋭の演奏家と指揮者を揃えたラインアップですが、比較的現代作曲家による作品が多いためか、特に日本ではそんなに人気のあるレーベルではないのが興味深いところです。
幸い、これらの技術とノウハウは、同レーベルのジャズやポピュラーのステレオ初期録音にも還元されていて、1956年から1958年頃までのスタジオ録音ものには、やはり鳥肌ものの盤が少なくありません (例えば Pete Rugolo の 1956年録音や、David Carroll の初期のパーカッション満載の録音など)。どちらかというとビッグバンドといった大編成の演奏の場合に当たりが多く、コンボ録音では首をかしげるものもあったりするのですが。
で,話を戻してこの盤.まずは良質の LP リイシューで定評のある Classic Records からの 200g 重量盤 LP を新品で購入しました。
1993年頃から Mercury のクラシック録音の CD リイシュー (432 012-2) が (Wilma Cozart ご本人による監修/リマスタリングの元) 行われたので、その時の 24bit ディジタルマスターからの LP ではないかと推測します。もしかしたら新規に (Wilma Cozart に協力を依頼して) アナログ 3ch マスターからカッティングしたのかも知れませんが (そういえばあまりディジタル臭さは感じなかった様な)。
で、ターンテーブルに載せて針を落とします。
. . .
オリジナルマスターテープ由来のヒスノイズの向こうから、本当に録音時の「空気」が聞こえてきます。「火の鳥」の出だしの弱音部分から、いや,もしかしたら、ヒスノイズが聞こえてきた瞬間からかも知れませんが、見事に音だけで鳥肌がたちました。曲後半 (B面) のオーケストラが爆発する辺りより、むしろ前半の方がリアリティを強く感じます。
しかもこの演奏、よくある「きれいに整い落ち着いた演奏」のまるで正反対で、もの凄く自由奔放なテンポでピアニッシモとフォルテッシモの間をジェットコースターの様にいったりきたり。隅から隅まで、全く飽きることがなく、ぐいぐいとひきこまれていきます。しかもこの時代のロンドン響、恐ろしい程「巧い」。まるで、艶めかしい輝きをもった切れ味抜群の日本刀を、目にもとまらぬ速さで操る剣士の様です。比較的地味な内容が続く A面ですら、その眩しいばかりの輝きに度肝を抜かされましたし、一体これのどこが地味な曲なの? って感じです。
Classic Records の再発 LP ですら (多分 CD もほぼ同じなんでしょう) こんな鳥肌が体験できたのですから、じゃあオリジナル盤 LP はどうなんだと思ってしまうのはレコードジャンキーの悲しい性。
TAS (The Absolute Sound、アメリカの有名なオーディオ雑誌) の高音質録音リストにながらく君臨しているだけに、ファーストプレスはさすがにいい値段します (とはいえ Frederick Fennell の “Hi-Fi a la Española” や Janos Starker の Suites for Unaccompanied Cello の 3LP ボックス程ではありません)。
. . .
えーい、と、例によって例の如く、あそこで入手。
![[SR-90226 Label Side-A]](https://microgroove.jp/img/SR90226A.jpg)
![[SR-90226 Label Side-B]](https://microgroove.jp/img/SR90226B.jpg)
ラジオ局用プロモ白レーベル.A面マトリックス末尾が FR1 A1、B面が FR3 A1。恐らくこれが真正ファーストプレスでしょう (B面 FR4 で、通常のダークマルーンレーベルの盤は確認済)。RCA Victor Indianapolis 工場プレスを表す I の刻印にも横線が重ねられておらず、まちがいなく Indy 工場プレスものでしょう。
で、緊張しながら針をおろすと。
. . .
マスターテープ由来のヒスノイズは、こちらの方が明らかに多い。B面最後の爆発部分はちょっと歪み気味。音の肌触りも、Classic Records の盤の方がマスターテープの音色に近いんじゃないかという感じ。
けれどもやはり、鮮度が圧倒的に高い (マスターテープは、どんなに細心の注意を払って厳重に保管していても、年を経るごとに情報が落ちていってしまうんだそうです) オリジナル盤の方が、A面のリアリティは圧倒的に上でした。再び鳥肌、そして思わず笑いながら涙を流してしまいました。
ところで、この両者の LP、カッティングレベルはほぼ同じなのに、デッドワックス (最内周の無音部) の幅が余りにも違い過ぎます。
特に大音量爆発の B面に顕著ですが、オリジナル盤の方は 5mm 程しか残っていないのに対し、Classic Records の方は 3cm 程余しています。カッティングマシンの性能が 40年の間に向上したのもあるのでしょうが、いわゆる可変ピッチでのカッティング (Variable Pitch Cutting、Mercury というか C.R. Fine さん的には Margin Control) のやりかたが違うのも関係していそうです。
Classic Records の方は、カッティング用マスターテープ再生ヘッドの少し手前に、音圧/音量検出用の補助ヘッドをつけたレコーダーで再生し、その補助ヘッドからの情報をもとに,カッティングヘッドの移動ピッチを自動調整しているんでしょう。
けれども、このオリジナル盤が録音されカッティングされた 1959年では、ピッチ調整は補助エンジニアが手動で行っていたんだそうです。Wilma Cozart が、楽曲の譜面や録音ノートを横目に、オリジナル 3チャンネルテープの出力を受けたミキサー/フェーダーを操作しつつ (とはいえカッティング中にフェーダー操作することはほとんどなかったそうですが)、補助エンジニアに「もうすぐ大音量のパッセージがくるわよ」と指示を出していたんだそうで (カッティング用に 2チャンネルテープにダウンミキシングしたのではなく、3チャンネルテープから直接カッティングしていたということです)、そうやってダイレクトミキシングしつつカッティングした結果がこれです。なので、ピッチの最適化というか効率は、最新のものに比べて劣るということなんですね。
Side-A: STRAVINSKY: The Firebird (complete ballet): Introduction and Scene I (beginning)
Side-B: STRAVINSKY: The Firebird (complete ballet): Scene I (concluded); Scene II London Symphony Orchestra, Antal Dorati (cond). Recorded at Watford Town Hall, London, England on June 7, 8 & 9, 1959. Wilma Cozart, recording director. Harold Lawrence, musical supervisor. C.R. Fine, chief technical supervisor. Robert Eberenz, recording engineer. Tape to disc transfer by George Piros.再び某雑誌の記事より。
“The Golden Age of Recording” (Michael Gray、嶋 護 翻訳) より:
. . . 録音の最高のハイライトは、じつは演奏が始まる前から訪れる。マスターに由来するヒスノイズが入った瞬間、リスニングルームは40年前のワトフォードのミニチュアになる。百人ほどの人間がざわめく軽い気配や空気が動く感覚は、ウィルキンソンやレイトンのベストの録音なら聴けるものなので、奇跡というには及ばないかもしれない。サウンドステージの鮮やかな表出も、他に求めることは不可能ではない。だが、天井の高さと後ろの壁の存在感さえがこうまではっきりと目に見えるような録音は、いったい録音の歴史すべてを通してもどれくらいあるのだろうか。少し踏み出せば、壁を触ることさえ別に難しいことではないようだ . . .
へい、うちのシステムではとてもそんな壁や天井なんか出てきやしません。まじで、ゆとりをもってセッティングできるリスニングルームが確保できる家に引っ越したいのう。いくら 4312 だからって、ちゃんとセッティングすればもう少しまともなサウンドステージを再現できると思うんだけどなあ。
後日談 (2006/05/03): 昨日 Refugee さん のお宅にお邪魔した際、この LP を持って行き、Refugee さんちのオーディオで聴かせてもらいました。 また別の種類の鳥肌キター。 エアボリュームたっぷりのリスニングルームって羨ましいですね、ホントに。 クラシック用のサブシステムが欲しくなったり、いやいや、それより前に、もっと郊外の広い住居に引っ越したいという気持ちが更に強くなるばかりでした。
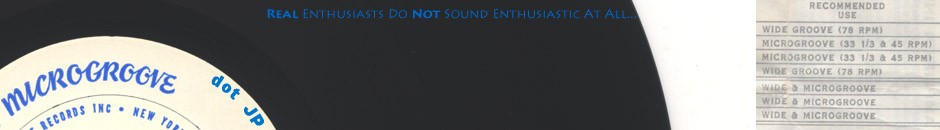
![[SR-90226 Front Cover]](https://microgroove.jp/img/SR90226_F.jpg)
![[SR-90226 Back Cover]](https://microgroove.jp/img/SR90226_B.jpg)
![[Firebird Dorati]](https://microgroove.jp/img/Mercury_Dorati_Firebird_F.jpg)