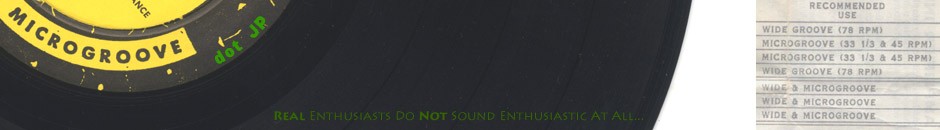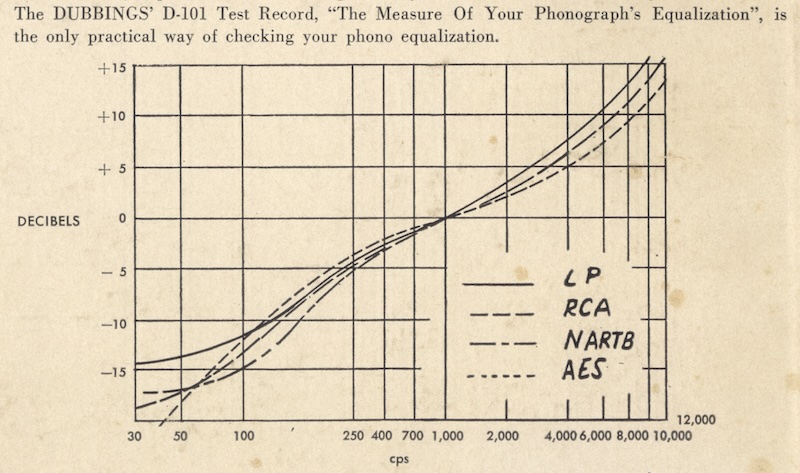TOPPING P50 Linear PSU (for Schiit Mimir)
Introduction, Pt. 2
知人の代理で購入した Schiit Mimir DAC についての続編です。
This post is a follow-up to my earlier article about the Schiit Mimir DAC I bought for a friend.
前回記事 の終わり で、次のように書きました。
At the end of the previous article I wrote the following:
以上の実験結果を知人に伝えたのですが、「モバイルバッテリの凄さは十分すぎるほど分かったが、時々充電しないといけないのはやはり面倒くさい」という返事でした。
I passed these test results on to my friend, but his reply was, “I totally get how good a power bank is, yet having to recharge it regularly – even if it’s only occasionally – is still a pain”.
そこで、次善策として、USB-C 5 V DC を取り出せるリニア電源ユニットを探してみることにしました。これならば、バッテリ駆動に近い結果が得られ、かつ充電の面倒臭さから解放されますので。
So as a fallback plan, I started looking for a linear power supply that can deliver 5V DC over USB-C. It should get us close to battery-powered performance without the hassle of regular recharging.
Schiit Audio Mimir Balanced Mesh™ DAC