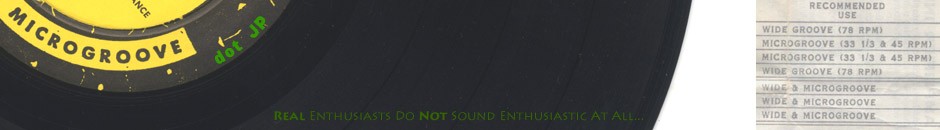うちのオーディオシステムの裏側で長らく生息していた、いつ頃どこで買ったのかもあまり覚えていないケーブル達。
こんなのとか:
![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/ortofon_rca_cables.jpg)
こんなのとか:
![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/mit_rca_cables.jpg)
を撤廃することにしました。代わりに、
Instagram 経由で知り合った Wagnus さんのところの Belden 89418 ケーブルに交換しました。
![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/belden_89418_rca_cables.jpg)
オーディオマニアの方々(別名オーディオ地獄に堕ちた方々ともいう?)は、あのケーブル、このケーブル、ととっかえひっかえして音質の違いを楽しまれるそうなのですが、私はそういうのは正直言って全く興味がありません。金持ちの道楽としてはいいんでしょうけど、そもそも「相対的な差」を評価して楽しむってのがよく分かりません。それだったら、10℃に冷やしたケーブルと30℃に暖めたケーブルの音質差を楽しむ、とかないんですかね。
ケーブルのさまざまな物理的特性によってアナログ信号の伝達特性が変わり、それが最終的な音の違いになるというのは分かるんですけど、だからといって「違い」だけを楽しむというのもなんかピントがずれているというか。
ともあれ、うちで使っている(特にこだわりのない)ケーブル達が、それぞれなんらかの癖を持っていて、どこにどれを繋ぐと音の出方が変わる、というのは事実なわけで。なんかすっきりしないというか、要はリファレンス的な「フラットな」ケーブルでいちどきちんと聞いてみないとなんともならないよね、というところに思い至り。
で、たまたま Wagnus さんのブログを拝見していたら、ちょうどそういう謳い文句のケーブル、「真のフラット音質、BELDEN 89418」があるのを見つけました。値段も比較的お手頃です(50cm ペアで 4,400円、1m ペアで 5,800円)。
というわけで、Wagnus さんおすすめの千住金属 RMA98-Super のハンダの組み合わせで作って頂いたケーブルをさっそく調達し、フォノイコライザ (Musical Surroundings SuperNova II) とプリメインアンプ (Triode VP-300BD) の間に接続してみることにしました。どちらのコンポーネントも機器としては音に癖はそれほどなく、入力ソースを素直に出力する系統といえます。
![[RCA cables]](https://microgroove.jp/img/SuperNova_Belden89418.jpg)
とにかくクセがなくて、下から上までくっきりすっきりのモニター的な音。特に高域の美しさとヴェールを剥いだような微細さがたまりません。それでいて高域寄りの音に聞こえず、帯域バランス的に全く破綻していないのは、ケーブル自体が本当にフラットな特性であるからと想像されます。このお手頃価格でこの満足度は素晴らしい(何度も言うように、ケーブルオタクではないですから、私。。。)。徹頭徹尾透明で色付けしない SuperNova のカラーが、更に引き立ちました。
手持ちの他のケーブルと繋ぎ直して比較試聴したりしても、やっぱり誰が聴いても明らかに差が分かるレベルでの違い。いままで「ジャズだと気持ちいいんだけど、クラシックだとなぁ」とか「Contemporary だと聴けるんだけど Blue Note がなぁ」みたいな、音源によって微妙にクセが出ていた出力が、どれもあっさり合格点を与えられるレベルに昇格したと言える(と勘違いしてしまえる程の)違い。
というわけで、あっさり他の系統も全部これにしてしまおうかと。
トーンアーム (SME 3009R) からフォノイコまでの経路は、純正付属の SME ケーブルをそのまま使い続けるとして、SP 再生時に通す Re-Equalizer の経路にも 50cm ペアを、そして (Michael さんの DAC プロトタイプなきあと暫定的に導入している、非常に廉価な中華製の) DAC の経路にも 50cm ペアを導入しました。
SP の音も、廉価 DAC の音も、これで更にすっきりくっきりしました。いやはや 89418 さん(というか Wagnus さん)ありがとうございます。
依然私のメインである、レコードを聴くという環境においては、スピーカーを除いてはまあこれでほぼ充分すぎるかなーと。スピーカーはいい加減 4428 か 4429 に替えたいところですが、やはり先立つものが。。。まあぼちぼちいきましょう。
DAC は Michael さんと心中する覚悟(笑)ですので、次期プロトタイプや最終製品を気長に待つ事にします。いちどあの アナログ的な音を聴いてしまったら、どんな高価な DAC であっても、16bit/44.1kHz な音源に関しては、全く満足できなくなってしまったといいますか。。。