2010年5月3日24時(4日0時)より再放送されます。お見逃しなく。
![[Soul Deep Episode 1: The Birth Of Soul] [Soul Deep Episode 1: The Birth Of Soul]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_001.jpg)
「ソウル・ディープ」NHK放送版は、オリジナルのBBC版から毎話10分程度カットして短く編集されています。その辺も踏まえて、以下第1回「The Birth Of Soul」(レイ・チャールズの回) に関する補足です (twitter でこつこつ書いていたもののまとめ & 補足修正版になります)。
注意: 本稿は、全体のまとめや批評などではありません。あくまで、個人的に興味を持った部分の情報を整理したもの、およびカット部分の特定をしたものです。ご了承下さい。
Rhythm’s OK In Harlem
![[Philips Broadcast of 1938] [Philips Broadcast of 1938]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_002.jpg)
「物語は1930年代のアメリカに始まります。」
というナレーションで始まる冒頭で流れた、黒人の人形がダンスするカラー映像。これはアメリカ人歌手・女優の イヴリン・ドール (Evelyn Dall) がイギリスの アンブローズ (Bert Ambrose) オーケストラにシンガーとして招かれ渡英していた時期に制作されたもの。
このショートフィルムは「Philips Broadcast of 1938」というタイトル。件の歌われていた曲 (なかなかにダンサンブルだけど若干軽めのアレンジ) は「The Rhythm’s OK in Harlem」。
当時SP盤でリリースされた録音 (Decca 675、いちおう CD リリース あり) より、このフィルム用の音源の方が更にアップテンポで聞き応えはあるように感じます。
また、今回調べる過程で、Evelyn Dall オフィシャル・ウェブサイト というものを発見しました。興味のある方はご参考までに。
![[Philips Broadcast of 1938] [Philips Broadcast of 1938]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_003.jpg)
なおこの映像と音源は、ストーリーとは直接関係あるわけではなく、単に当時のアメリカの黒人の状況をそれらしく映像表現する為、BBC がイギリスの当時のフィルムを使っただけと思われます。
Green Corn
![[Cottonfields and a cottage] [Cottonfields and a cottage]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_004.jpg)
「レイ・チャールズ・ロビンソンは1930年9月23日アメリカの南部ジョージア州のオルバニーで生まれました」
とナレーションが入るシーンで流れるフォークブルース「Green Corn」、この音源、誰の演奏か最初は分かりませんでした。なんか一番有名なレッドベリー (Leadbelly) の「Green Corn」とも違うし、Josh White でも Big Bill でもなさそうだし、誰の演奏なんでしょうこれは。。。と思っていたのですが。
twitter 上で yaging さんが特定して下さいました。やはり レッドベリーで正解で、1940年8月23日、国会図書館用録音のテイクでした。情報ありがとうございました。(手元にあるレッドベリーの Green Corn の音源がもっとアップテンポで荒々しいバージョンで、気がつきませんでした。失礼しました…)
Moten Swing
![[young Ray listening to a radio] [young Ray listening to a radio]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_005.jpg)
例の友人、ジョー・ウォーカー (Joe Walker) 氏が「将来、俺がラジオでお前の音楽を紹介してやる」といったエピソードを語る場面。かかっているのはカウント・ベイシー (Count Basie) の有名曲「Moten Swing」(1940)。
「Moten」というのは、ベイシーが1929年にメンバーとして加入したオーケストラのリーダー、ベニー・モーテン (Bennie Moten) のこと。このバンド、Bennie Moten’s Kansas City Orchestra の1932年12月13日録音「Moten Swing」は こちら (jazz-on-line.com) で聞けます。
その後1935年にモーテン逝去、そのバンドを引き継いだのがベイシーというわけです。錚々たるメンバーによる完璧なソロと鉄壁のリズムセクション、抑制されつつも効果絶大な御大のピアノ。戦前ジャズの至宝。かつ戦後直後のホットスウィング系の規範。影響多大。書き出すと長くなるのでこの辺でやめときます(笑)。
てっとり早く安価にベイシー全盛期の音源を概観するには、お馴染み Proper Music の4枚組「The Count Basie Story」あたりがお勧めです。
1940年というとレイ・チャールズ自身は10歳。ラジオからかかるさまざまな音楽に夢中になりピアノに向かっていたのでしょうね。
Louis Jordan, The King Of The Jukebox
![[Ray Chales / Louis Jordan] [Ray Charles / Louis Jordan]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_006.jpg)
この回で個人的に一番嬉しかったのは、ルイ・ジョーダン (Louis Jordan) が第0回と言える程に大々的にフィーチャーされていたこと! Ray と Louis の「Let The Good Times Roll」が交互にかかる編集はシビれた!
![[James Brown / Louis Jordan] [James Brown / Louis Jordan]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_007.jpg)
そして我らが尊師 ジェームス・ブラウン (James Brown) が Louis Jordan について語るシーン。ジャンプミュージックはファンクの父だ! いやホント。
なお、サウンディーズなど (当時の黒人ミュージシャンとしては比較的) 豊富に映像が残っているルイですが、今回かかったのは定番どころのお馴染みの楽曲群。「Let The Good Times Roll」「Honey Chile」「Caldonia」「All For The Love Of Lil」といった辺りです。
Louis の全盛期 Decca 時代の定番を収めた CD といえば この辺り でしょうか。音質的に苦手な方は、1956年録音の「Somebody Up There Digs Me」がお勧めです。クインシー・ジョーンズ (Quincy Jones) がアレンジャーとして参加しています。
Ray Charles and Quincy Jones
「15歳の時(1945年)には当時のあらゆる有名ピアニストのスタイルでピアノを弾くことが出来ました」
というナレーションの件。特に有名なのはナット・キング・コール的トリオ演奏で、レコードデビュー直後の音源は 2枚組CD (なぜか私が持ってる盤とジャケットが異なりますが) にまとめられておりこの頃の模索を伺うことができます。
1949年 The Maxin Trio としての Down Beat / Swing Time レーベルへの録音に始まるこの2枚組で、お馴染みレイ・チャールズのスタイルに至る変遷をたどることができます。
なお、長年の盟友となる3歳年下の クインシー・ジョーンズ (Quincy Jones) と知り合ったのは1947年シアトルでのこと。先輩としてレイは若きトランペッタークインシーに多大な影響を与えたそうです。
「クインシー・ジョーンズ自叙伝」(中山啓子訳) をみると、この当時の興味深いエピソードが記されています。
レイは私の鑑だった。
という一文に全てが象徴されているように思えます。
(レイは) ピアノを弾きながらナット・キング・コールやチャールズ・ブラウンばりの歌を聴かせ、アルトサックスでビバップを吹けばチャーリー・パーカーを彷彿とさせた。かと思えばピアノに戻ってバド・パウエルの様なソロを弾いた。
Roy Bird aka Professor Longhair
アトランティック (Atlantic) レーベル / アーティガン兄弟 (Ahmet & Nesuhi Ertegün) が紹介される場面でかかっているのは「Longhair’s Blues-Rhumba」(1949)。いうまでもなく、ニューオーリンズが生んだ偉大なミュージシャンのひとり、プロフェッサー・ロングヘア (Roy Bird, aka Professor Longhair) の最初期の録音のひとつです。
フェスの定番としては、ドクター・ジョン (Dr. John) が実質的プロデュースした遺作「Crawfish Fiesta」(1979年録音) でしょうが、キャリア総括的な 2枚組CD「Fess: The Professor Longhair Anthology」 が、ライナーも丁寧でお勧めです。
1949年に始まる Star Talent、Mercury、Federal、Atlantic 等の初期録音はどれも極上の出来ですが、1947年にニューヨークを拠点に設立されたマイナーレーベル Atlantic が、ニューオーリンズ R&B にちゃんと注目していたのは素晴らしいことです。
以下余談。戦後直後は、アメリカでマイナーレーベルが特に雨あられの様に大量に生まれた時代。戦前のビッグスリー:デッカ、ヴィクター、コロンビア。最初に立ち向かったビッグマイナー (今ではメジャー) が1942年設立のキャピトル。続いて1945年設立のマーキュリー。
メジャーに対抗しようと生まれた「スーパー・インディーズ」は、全米各地のあらゆるジャンルを網羅するべく、ディストリビューション網整備やスカウトに余念がなかったのですが、その他大量のマイナーレーベルが全米中に存在し、演奏家に多くの録音の機会が与えられることになりました。
これらマイナーレーベルが存在していてくれたからこそ、今の世に当時の幅広い音楽 (の一部) が残され、我々は妄想をたくましくしながら当時の息吹の一端を脳内再生することができる。録音再生技術万歳!
The Jukebox Tags
![[Jukebox tags] [Jukebox tags]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_008.jpg)
アーメット・アーティガン (Ahmet Ertegün) 氏のインタビュー場面 (NHK版だと開始18分頃、BBC版だと15分半頃) で映っている、78回転 SP のジュークボックスタグ。なんとなく気になったので、誰のなんて曲が入ってるのか、拾い出してみました。
- Pretty Mama Blues / Ivory Joe Hunter
- Trouble Blues / Charles Brown Trio
- Tomorrow Night / Lonnie Johnson
- Am I Making The Same Mistake Again / Ruth Brown
- Sixty-Minute Man / The Dominoes
- Chains Of Love / Joe Turner
- I Don’t Know / Willie Mabon
- Boogie Chillun / John Lee Hooker
- R.M. Blues / Roy Milton
- Saturday Night Fish Fry / Louis Jordan
- Caldonia / Louis Jordan
- I Can’t Go On WIthout / Bull Moose Jackson
- Fool, Fool, Fool / The Clovers
- (その他)
うーむ、なんてステキなラインアップでしょう。
Miss Rhythm Ruth Brown Sings
![[Ruth Brown sings on stage] [Ruth Brown sings on stage]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_009.jpg)
開始18分40秒頃(NHK版、BBC版だと16分頃) の ルース・ブラウン (Ruth Brown) の映像。これは1955年収録の「Showtime At The Apollo」からの映像。ホストはウィリー・ブライアント。
この映像の「Mama, He Treats Your Daughter Mean」は、当時シングルリリースされたものより超アップテンポで迫力満点。バックはポール・ウィリアムス (Paul “Hucklebuck” Williams) バンド。ブリブリホンカー Paul Williams のバンドとマッチして最高の歌唱を披露しています。
Paul Williams は当時 Atlantic レーベルのハウスバンドとして活躍 (自己名義の大ヒット “The Huckebuck” は1949年)。のちには James Brown の音楽ディレクターを務めたことも。
いうまでもなく Ruth Brown は Atlantic 初期、Ray Charles より先に大ヒットを飛ばし、レーベルを軌道に乗せたドル箱スター。この時の映像は他に「Oh What A Dream」「Raining Tear Drops From My Eyes」「Have A Good Time」が存在。他のミュージシャンも興味深い人達が多数参加。全部観たい!
余談ですが、このホストの ウィリー・ブライアント (Willie Bryant) のバンドによる、1930年代の録音が大好きで、以前「Mary Had A Little Lamb / Willie Bryant」という記事を本ブログに書いたこともあります。
ずっしりとしたリズムセクションなのに、全体的にジャイブ風味たっぷりで軽やか。茶目っ気たっぷりでキャッチーだけど、演奏者の腕は確か過ぎ。アンサンブルは鉄壁過ぎ。ええよなぁ。
Chitlin’ Curcuit
![[Chitlin' Circuit] [Chitlin' Circuit]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_010.jpg)
NHK版19分頃 (BBC版17分辺り)、黒人ミュージシャンがツアーした全米の一連の会場をチトリン・サーキット (Chitlin’ circuit)と言いますがが、この Chitlin’ は伝統的ソウルフード Chitterlings (豚のモツ煮、チタリング) に由来するとのこと。
![[Howlin' Wolf? on Chitlin' CIrcuit?] [Howlin' Wolf? on Chitlin' CIrcuit?]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_011.jpg)
NHK版21分48秒辺り (BBC版19分14秒辺り) に、ちらっと ハウリン・ウルフ (Howlin’ Wolf) とおぼしき人のステージ映像が写ってますが、オーディエンスのカラー8mm映像 (音声無) とかなんでしょうかね。雰囲気からして1960年代中頃のものでしょうか?
カットシーンその1 (少しだけ)
BBC版20分半辺り (NHK版23分辺り)、NHK版ではここで40秒ほどカットされています。主に、当時の歌詞についての話題です。
ルース・ブラウン:
「この頃ってまあダーティだったのよ。ある類の曲はラジオでは絶対かからなかったし。」
レイ・チャールズ:
「セクシーな歌詞は良く歌われた。ダブルミーニングになってね。どっちの意味をとるかは自分次第。例えば『きみのかわいいプードルちゃんと遊びたいぜ』という歌があるけど、プードルのことなんか歌ってないわけでね。」
Boss Of The Blues, Big Joe Turner
![[Big Joe Turner singing on stage] [Big Joe Turner singing on stage]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_012.jpg)
…といったカットシーンののち、NHK版でも放送された ビッグ・ジョー・ターナー (Big Joe Turner) の「Shake, Rattle & Roll」のシーンへ。これも当時の代表的なセクシーな歌詞。兄弟曲の「Flip, Flop & Fly」はもっとセクシー。
このビッグ・ジョー・ターナー歌唱シーン(バックはポール・ウィリアムスバンド)は、先日紹介したルース・ブラウンのと同じ映像「Showtime At The Apollo」より。
カットシーンその2 (大幅)
NHK版32分39秒辺り(黒人白人観客間にロープが張られていたエピソード、警官に砂漠の真ん中に取りのこされたエピソード、チトリンサーキットを離れて自分のバンドを作る決心をしたエピソード、などのあと)に大幅にカットされた部分あり。以下詳細。
Ray の「The Sun’s Gonna Shine Again」がかかる中、
ナレーション:
「レイは、自身のキャリアを更に一段レベルアップするために、まだ多くの事を学ばなければならなかった。既に R&B の世界では一定の成功はしていたものの、更に一歩進んでポップマーケットでの成功を望んでいた。」
ナレーション:
「黒人アーティストでそれを行った数少ない先駆者の一人が、ファッツ・ドミノ (Fats Domino) であった。」
ここからファッツ・ドミノが大フィーチャーされます。
![[Cosimo Matassa on Interview] [Cosimo Matassa on Interview]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_013.jpg)
「Blue Monday」(スタジオ録音)がかかるなか、あの コズィモ・マタッサ (Cosimo Matassa) のインタビュー:
「当然ながらファッツはユニーク(唯一の存在)。みんな彼の素晴らしい音楽に夢中だった。」
![[Fats Domino playing Sunday Morning] [Fats Domino playing Sunday Morning]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_014.jpg)
そこで映画「The Girl Can’t Help It」(1956) の演奏シーンに移り、マイケル・ライドン (Michael Lydon) のコメント:
「彼の音楽の魅力はノリノリのダンスビート。それに彼は太っちょだった。当時のショービズ界では常に彼が『Jolly Fat Man』だったわけ。」
. . . もう少し時代を遡るとその地位はファッツ・ウォーラー (Fats Waller) だったのかな、やっぱり?
続いて今度は アラン・トゥーサン (Allen Toussaint) のコメント (本来のインタビュー全体からかなり前後がカットされてるっぽいけど)。
![[Allen Toussaint on Interview] [Allen Toussaint on Interview]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_015.jpg)
トゥーサン:
「男性にとって当時のクルーナー歌手は脅威だった。女性はみんなクルーナーにメロメロだったし、男性はそれが面白くなかった。けどファッツの音楽は誰にでも受け入れられた。母親、祖母、息子、誰にだって。そして誰にとっても脅威でない音楽だった。」
ナレーション:
「ファッツの音楽と立ち振る舞いにより、彼は愛すべきエンターテナーとして記憶されることになった。しかしその実は、類い希な才能を持ったミュージシャンであり、ニューオーリンズピアノサウンドをメインストリームに紹介したイノベータであった。」
![[Allen Toussaint on Piano] [Allen Toussaint on Piano]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_016.jpg)
トゥーサンが「Blueberry Hill」を弾きながらナレーションがかぶる:
「ファッツのピアノは非常に真似しやすいスタイルで、すぐにポピュラーになった。ファッツがツアー中、トゥーサンも代役としてスタジオ録音に参加を要請されたこともあった。」
トゥーサン:
「私はファッツの音楽・スタイルから外には出なかった。それでうまくいったし、みんなそれが私のスタイルだと分かってくれた」「ファッツの音楽スタイルは真似しやすい。彼が座り、ピアノを弾き出すと、これこそ求めてたものだ、と皆口を揃えたものさ。」
トゥーサンの弾く「The Fat Man」から蓄音機でかかるファッツの同曲に切り替わり、それを聴きながら アール・パーマー (Earl Palmer) のインタビュー。彼はファッツ・ドミノの初録音以降ほとんどのレコーディングでドラマーを務めた他、リトル・リチャード (Little Richard) の多くの録音、プロフェッサー・ロングヘアー、ロイド・プライス、スマイリー・ルイス、その他数え切れない程のニューオーリンズ系セッションで大活躍した名ドラマー。ちなみに「The Fat Man」はファッツ・ドミノのデビュー曲です。
![[Earl Parmer on Interview] [Earl Parmer on Interview]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_017.jpg)
パーマー:
「『The Fat Man』、そう、1949年に彼が録音した曲だ。『Detroit City Blues』がカップリング曲だ。」
(歌詞が「I was standing on the corner」という箇所の「corner」が「condor」っぽく聴こえるところにさしかかると)「『コンドルに立ってた』だってよ!」と笑いながら懐かしそうに語るパーマー氏。残念ながら2008年9月19日に鬼籍に入られました。
(歌詞が有名な wah wah wah パートに入ると) パーマー:
「ここは素晴らしいよね。ファッツ流のヨーデルだよ。レコーディングの時、ベースのフランク・フィールド (Frank Field) が『奴は録音中なのになんで奇声出してんだよ!』ってびっくりしてたね。それで奴はコードチェンジし損ねてんだよ (笑)」
余談ですが、このファッツのデビュー曲にして名曲「The Fat Man」、トラディショナルソングの「Junker’s Blues」を基に作られた曲です。チャンピオン・ジャック・デュプリー (Champion Jack Dupree) の 1940年録音「Junker’s Blues」なんて、ヨーデル部分がない以外はモロにファッツの「The Fat Man」そのまんまなのが面白いです。というか、どっちも失禁ものの格好良さ!
ナレーション:
「ファッツは、ポップマーケットにもクロスオーバーヒットを放った最初期のアーティストとなった」「1950年代中頃になると、全米の白人向けラジオ局でも R&Bがかかるようになっていた。肌の色さえ、製品の宣伝に使うこともあった。」
![[McTavish's skinless weenies] [McTavish's skinless weenies]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_018.jpg)
というナレーションの直後、ラジオ放送ブースでDJが読む映像が流れます「… and now let me tell you about McTavish’s skinless weenies. Mm-mmm. So long, so pink, so flavor rich…」なんか割と有名な映像っぽいですが、この白人DJさんのゆうてること、結構下ネタ的というかキワどいことのような。。。ホットドッグの宣伝のようで、実はあれのことをゆうてるような。。。この映像がここで使われた意味ってのは、R&B (ここでは The Fat Man ) をかけた直後に、ホットドッグの宣伝文句を話す → R&B を宣伝に使ったりした、ってことだと思うんですけどね。
![[Little Richard singing Ready Teddy] [Little Richard singing Ready Teddy]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_019.jpg)
ナレーション:
「1956年、今度は リトル・リチャード (Little Richard) が銀幕を席巻し、白人達は恐怖に襲われることとなった。」
映像は再び映画「The Girl Can’t Help It」より「Ready Teddy」演奏シーン。
マイケル・ライドン (Michael Lydon) のコメント:
「当時にはセクシー過ぎた。『Trutti Frutti』の話を食事中になんか出来ない。余りにも自由過ぎ、余りにも汗まみれの音楽だった。」
![[Alan Freed] [Alan Freed]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_020.jpg)
ナレーション:
「R&Bは徐々に人種の垣根を越え、白人の若者の生活スタイルにも影響を与えだした。DJ アラン・フリード (Alan Freed) が R&B を「ロックンロール」という言葉で再定義したことが、この影響に拍車をかけた。」
ここで第1回の主人公たるレイが再びインタビューで登場。レイ・チャールズ:
「このことにはあまり言及したくなかったからもう二度と言わないぜ。『R&R は白人版 R&B だ』ってか。まあいい、俺が真実を教えてやろう。R&R は黒人 R&B から生まれた『分家』(offshoot、子孫) ってことだ。」
ルース・ブラウン:
「リトル・リチャードが言ってた。『R&Bと呼ばれる音楽があった。その音楽にはR&Rという名の子供がいた』ってね。」
ナレーション:
「アメリカの白人ティーンエージャーは、ワイルドで自由な R&R のサウンドのとりこになった。そしてこのことを、確立された白人社会を黒人文化が脅かし始めたと受けとる者もいた。」
ブランフォード・マルサリス (Branford Marsalis) のインタビュー:
「アラン・フリードが先陣切って、黒人音楽を白人向けラジオ局でかけたりしたのは、当時の上流階級 (genteel folks) にはちと厳しかったんだろうね。」
![[Asa Carter] [Asa Carter]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_021.jpg)
当時の有名な映像、アサ・アール・カーター氏の発言が映る:
「黒人R&Rは明らかに、白人およびその子供達に悪影響を与えるものだ。」
![[white DJ breaks 78rpm] [white DJ breaks 78rpm]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_022.jpg)
別の初老白人男性 DJ (?) の映像では「黒人 R&R のレコードなんてこうしてしまえ」と、SP盤をターンテーブルから外して叩き割ってしまいます。
ナレーション:
「安全で除菌されたバージョンのR&Bの名曲達は、ジョージア・ギブス (Georgia Gibbs) などの白人アーティストによって白人向けに生み出されていった。」
![[Georgia Gibbs sings] [Georgia Gibbs sings]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_023.jpg)
映像はギブスの「Tweedle Dee」歌唱シーンです。こういう文脈で観る・聴くのでなければ、悪くない歌唱だと思います。というかうちにはギブスのLP何枚もあります (笑)。
ルース・ブラウン:
「私の『Three Letters』って曲があって、ギブスがカバーしてた。ある時アラン・フリードのラジオ番組に出演したら、ギブスも来てた。で、ギブスがその曲を歌ったのよ。私は別の曲を歌わされた。当時はそんなんだったわ。」
ギブスの「Dance With Me Henry」歌唱シーンにかぶさる エタ・ジェームス (Etta James) のインタビュー:
「ギブスが私の15年前の曲『Roll With Me Henry』を歌うことには反対だったの。歌詞が性的隠喩的だし。」「だって『Roll』With Me Henry よ。それを彼女は『Dance』With Me Henry と歌いかえたというわけ。」
![[Bill Haley and His Comets] [Bill Haley and His Comets]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_024.jpg)
ビル・ヘイリー (Bill Haley) の「Shake Rattle and Roll」演奏シーンにかぶさるナレーション:
「こうやって次々と黒人R&BヒットがクリーンなR&Rとして白人ミュージシャンにカバーされていった」
まあこういう (ややもすれば一方的・一面的な) 描き方・話の紡ぎ方が、とってもBBC的といいますか。。。
再びレイ・チャールズのインタビュー:
「両者には大きな違いがある。聴けば分かる。一方はよりピュアな音楽。かたやよりダーティな音楽。ブルースとR&Bには足の垢 (toe jam) が詰まってる… R&R はもっとピュアでクリーンな音楽だ。分かったか?ガハハハ!」
…ということで、ここまでが、NHK版 Soul Deep 第1回放送で大幅カットされたパートの内容でした。このあと、レイがドラッグに手を出していた話へと繋がります。
カットシーンその3 (少しだけ)
NHK版37分40秒辺り(レイの「Ain’t That Love」が BGM でかかりながら、ゴスペルを再発見するエピソードの紹介部分と、「I Got A Woman」演奏シーンの間)に、40秒程度と短いながら、重要なカットシーンがあります。
アラン・トゥーサン再び登場、「Ain’t That Love」を弾き語りしてくれてます。満足そうに弾きながらトゥーサン氏曰く: 「…そう、これはモロにゴスペルだよね。『ゴスペル』と『レイ・チャールズ』。この両者は不可分のものなんだよ。」
Ain’t That A Groove
NHK版41分30秒辺り (BBC版49分30秒辺り) のジェームス・ブラウン (James Brown)「Try Me」映像は、お馴染み1968年4月5日、ボストンガーデンでのライブ より。
![[James Brown on stage] [James Brown on stage]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_025.jpg)
NHK版42分15秒辺り (BBC版50分15秒辺り) のジェームス・ブラウン (James Brown)「Please Please Please」映像は、これまたお馴染み1964年のT.A.M.I. Showより。T.A.M.I. Show 出演時の完全版映像はこちら (YouTube):Pt.1、Pt.2、Pt.3。
カットシーンその4 (少しだけ)
NHK版最後 (What I’d Say演奏シーンの後) にカットされた部分あり。ボビー・ウォーマック (Bobby Womack) のインタビュー。
![[Bobby Womack on Interview] [Bobby Womack on Interview]](https://microgroove.jp/img/SoulDeep_1of6_026.jpg)
ウォーマック:
「彼 (レイ・チャールズ) はまぎれもない天才だった。彼が世界を変えた。彼がいなければソウルミュージックはなかった。彼が扉を開けたんだ。」
ナレーション:
「『What I’d Say』から、R&Bは黒人オーディエンスだけのものではなくなった。レイはその後カントリー、ジャズ、ブルースなど幅広いジャンルに進んだが、今に続く『ソウル・ミュージック』の誕生に最も寄与したミュージシャンである。」
( . . . 第2回補足に続く . . . )
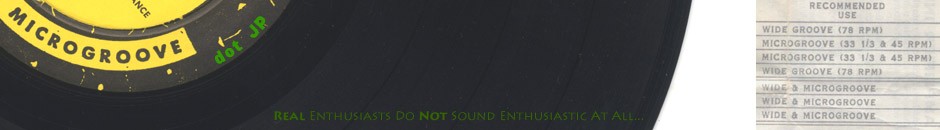
![[Somebody Up There Digs Me / Louis Jordan] [Somebody Up There Digs Me / Louis Jordan]](https://microgroove.jp/mercury/img/MG20242_F.png)
![[Bluebird 6435] [Bluebird 6435]](https://microgroove.jp/img/BlueBird6435s.jpg)
松林さん
おひさしぶりです。いやあ、この補足資料、すばらしい。時間かかったでしょう。おつかれさまです。引き続き、第6回まで楽しみにしています。
よしおか
吉岡さん、恐縮です。
再び時間ができたら、続きも書こうと思います。
第5回までは、ほぼ補足する内容も頭の中で把握できてますし。
問題の第6回はどうしたものか。。。補足だらけになったりして。
第6回補足は、より詳しい方にバトンタッチした方がいいかもしれません。
(番組的にも第5回までとの乖離が激しかったですが、私の知識も。。。笑)