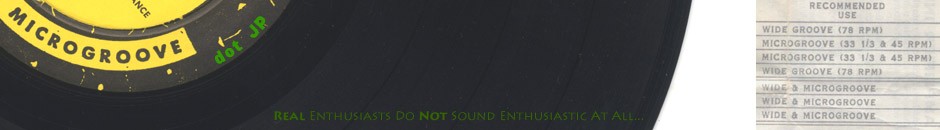1970年代〜1990年代〜2010年代の見事なブレンド。ジミヘン・ミーツ・JB。ハードボッサファンク。ヒップホップロック。ジャズファンク的ハードロック。このバンドの3枚目となる新作をひとことで形容することは不可能です。バラエティ豊かな音楽的背景が見え隠れする一方、図太い一本筋の通った個性と主張が眩しいくらいに光ります。
スピーカー・サージェント (Speaker Sgt.)。「スピーカー軍曹」という不思議なバンド名は、いやがおうにもロックっぽいイメージを喚起させます(そういえば、本家本元のペッパー軍曹(笑)の方は、つい先日 50周年記念デラックスエディション が出ましたね)。
その音は、ロック、ファンク、ジャズ、ヒップホップなど多種多様なジャンルが渾然一体としたもので、ジャンル分けの無意味さを強く主張しています。
デビュー作「Speaker Sgt.」(2010)では、Ronny Jordan Meets Madlib といった風情の強力ジャズファンクという印象でした。その翌年にリリースされた、フュージョン名曲をグルーヴ感たっぷりにカバーした2作目「FREAK! The Other Side of Fusion」(2011)ののち、ドラマーが交代し、長い充電(?)期間を経て世に問われた本作。
メンバー3人の多種多様な音楽的背景が有機的に結実して、強力な個性として確立しており、素直に圧倒されます。
リーダーの 越智巌 さん。私が越智さんの演奏を初めて観たのは、今はなき西日暮里のエディーズ・ラウンジにて、ファンキーなソウルジャズをエディー・ランズバーグ (Eddie Landsberg) のカルテットで演奏するレギュラーセッションでのことでした。とにかく様々な音楽への思い入れ、造詣の深さが、確かな技術で演奏されるギターに滲み出てこられる、素敵なギタリストです。
初めてお話しさせていただいたとき、そして、演奏を聴かせていただいたとき、まずもってリスナーとして相当いろんな音楽ジャンルを自由に聴き込まれてるんだなと感じました。

Masahito Hando (ts), Eddie Landsberg (org), Iwao Ochi (g), Atsushi Harada (ds).
live at Eddie’s Lounge, Nishi-Nippori, Tokyo on Sep. 3, 2014

Iwao Ochi (g), Naoto Nishikawa (org), Kazuaki Yokoyama (ds).
live at Organ Jazz Club, Numabukuro, Tokyo on Mar. 13, 2015
そんな越智さんは、もともとロック方面からギターに入られ、ブラックミュージックの追求のため5年間渡米、そこでジャズギターを専攻しピーター・バーンスタイン (Peter Bernstein) さんらに師事しつつ、、あのサム・ヤエル (Sam Yahel) さんとデモ音源を作ったりもしていたそうです。その一方、ロニー・ジョーダン (Ronny Jordan) さんなどNYクラブ・ヒップホップシーンの洗礼も受け、トラック制作を開始されたそうです。どんなジャンルを演奏されるときにもホンモノのグルーヴ感が常に通底しているのが本当に素晴らしいです。
残念ながら、直接お会いしたりライブを聴かせていただいたことはまだないのですが、ベースの 梅沢茂樹 さんもジャズ、ファンク、ロックなんでもござれ(笑)的な巧さが強力に伝わってきますし、キース・ムーンがフェイバリットというドラムスの 佐藤大輔 さんもまた、ジョン・ボーナムがあのファンク大名曲の「The Crunge」を演奏している時のような、自然で体からほとばしるジャンルミックス感を彷彿とさせます。お三方とも、相当広範な音楽の影響を受け敬愛(溺愛?)されていることが、音源から痛いほど伝わってきます。
三位一体となって繰り出される、自由奔放なノリ。こんなグルーヴを自然体で出せるバンドって、日本ではなかなかお目にかかれないんじゃないでしょうか。
「オトナファンク」あるいは「ヒップホップジャズ」と形容されますが、まずもって一体感溢れるバンドであることが圧倒的です。
さて、本アルバムですが、とにかく最初から最後まで全く飽きさせない、何度聴いても飽きようがない、バラエティに富むものとなっています。ラジオジングル、あるいはインタールード的なショートトラック、そして長めの本編、これらがほぼ交互に配置されており、しかもそれぞれの楽曲のバラエティが素晴らしい。多方面に向かう音楽的ベクトルが心地よいです。
どの曲を取り出しても、その中にはマルチジャンルな要素が詰まっています。さらに、それぞれの曲同士もダブり感が全くなく、アルバム全体としても豊かな多様性を感じさせます。
かつ、バンドのアイデンティとしてホレボレするほど一本筋が通っているのです。
古今東西、オールジャンル(もちろん貴賎なく)、いろんな音楽を雑食的にディグするのが大好きな私の音楽的嗜好に、ドンピシャリではまりました。ファーストもセカンドも聴かせていただきましたが、このサードの完成度、満足感たるや、それらを圧倒してるんでじゃないか、という印象を持っています。
これから聴かれる方のために、あまりネタバレにならないようにしたいところですが(笑)各曲のざっくりとした印象を。
1曲目「Intro」のアシッドジャズ / ヒップホップ感満載のコラージュでぐっと期待を膨らませておいて、重心の低さとグルーヴ感がドハマりのファンキーロック、2曲目「Bad Baby Strut」でまずノックアウトされます。控えめな出番ながら静かに爆発してる感じの Eddie のオルガンがいいですね。随所の赤ちゃんの声もアクセントになってますし、アウトロの女の子のぶっきらぼうな会話も面白いですね。
まったり系ファンクなインタールードの3曲目「Interlude 1」を挟んで、重量級ファンクの4曲目「Outfield」。キーが「Bad Baby Strut」と同じGなので、連続性を強く感じさせつつ、こちらは7拍子ファンクです。音の感触はハードロック、特に Zeppelin を彷彿とさせるもので、越智さんのギターは無限にファンキーなソロを紡ぎ出せそうな感じです。
そして5曲目の「Digital Destruction」。ガットギターのリフで静かに始まったかと思うと、いかにもヒップホップ然としたリズムセクションがフェードイン、ラップと融合する瞬間が白眉です。切り刻み方、構築方法が実にナイスです。
ローファイなギターリフから始まる6曲目「Troit」は、実に面白いリフのギターと、抜き気味のドラムスがポリリズミックに絡みながら進むさまがスリリングでたまりません。いかにも現在進行形なファンク・ロック・ジャズ的な趣です。
ラジオジングルのような効果抜群のループコラージュ系ヒップホップトラック、7曲目の「Need Your Imagination」をはさみ、どファンキーなドラムパターンがクセになる、ロック感満載なアレンジの 8曲目「Chestnut Head」。ブレークあたりで「いわゆるフュージョンっぽさ」がにじみ出ていますが、それでも全く軟弱系に行かないのが、3人の演奏がタイトでファンクグルーヴが共有されている証でしょう。ドラムの重さはやっぱり Bonham 系?(笑)
ディストーション多めの本アルバムの中で珍しくクリアな音触でのマスタリングの「Interlude 2」の次に、またまた Zeppelin っぽいギターと重量系ドラム&ベースで始まる 10曲目「Green Dive」は、イントロを過ぎると比較的軽やかな印象ですが、やっぱり重たい重たいグルーヴ感が素晴らしいです。雰囲気としては、かつての大野克夫バンドなどに通じるものも感じます。随所のブレイクもナイスで、ライブ演奏をそのまま聞いてるような感覚になります。後半のギターソロでのタンバリンが JB の Hot Pants(をスローにした感じ)に聞こえると思ったら、越智さんのギターもそれっぽく聞こえてくるのが不思議です。なのにやっぱりジミヘンっぽい雰囲気も醸し出されていて、こういったあらゆる音楽ジャンルのエッセンを体得ししかも全てオリジナルなかたちで表現されるのは本当にすごいと思います。
エレピといいリズムフィギュアといい、いかにも1970年代ジャズファンクへのオマージュ的な良質な「Interlude 3」の次は、12曲目「Blind Street」。印象的なブレークを効果的に使用したシンプルなリフが徐々に変化しながらギターが飛び回ります。後半のエフェクトも効果的。1970年代〜1990年代〜2010年代が自由自在に融合しているさまが本当にかっこいいです。
ジミヘンの有名なセリフをループした、ヒップホップっぽいインタールード「This Is It」の次が、私が個人的に一番お気に入りの14曲目「Slow Joint」です。ハードボッサと JB の Give It Up Or Turnit A Loose(あるいは Blackbyrds の Rock Creek Park?)が奇跡の融合か?的な相当面白い演奏です。ガットギター、ロックギター、そしてファンキーなカッティング、パーカッション、そのどれもが見事に有機的な絡まりでどっしり迫ってきます。そしてこの曲でのドラムスとベースの仕事っぷりが本当に素晴らしいです。
Clyde 風ドラムスと Bootsy 風ベースがオルガンと絡む、ナイスなファンクジャズ「Interlude 4」の次が16曲目「Afro Spice」。イントロのギターリフと音色が、モロにジミヘンオマージュ?と思いきや、そのままご機嫌なファンクジャズロックへと突入。3人のタイトな絡みあいがたまりません。
ヒップホップなインタールード「Beautiful」でクールダウンしたあとは、最後の18曲目「Black Snow」へと続きます。このギクシャク感がたまらない重量級スローなファンクロックはどうでしょう。なにより三者三様のリズムの「ゆらぎ」が心地よいです。いつまでも聴き続けていたい、けど唐突に終わるのも意表をついてきます。
どの曲をとっても、ディープな音楽マニアが聴くとニヤリとできる瞬間で溢れていて、しかも日本人離れした(?)グルーヴの演奏で圧倒されます。それでいて、(良い意味での)キャッチーさが随所にあふれていて、万人に広くお勧めできる好盤でもあります。いやーいいアルバムに出会えてホントに嬉しいです。
最後に、2017年5月に、越智さんにオンラインで行なったインタビューというか質問を載せておきます。演奏活動でお忙しいところ、本当にありがとうございます。
 Q1: 「This Is It」では、Jimi Hendrix の Monterey Pop Festival の有名なセリフがサンプリングされていますが、一方、「Afro Spice」のイントロのギターリフはジミヘンオマージュ的な音の感触です。これは意識されてそうされたのでしょうか?
Q1: 「This Is It」では、Jimi Hendrix の Monterey Pop Festival の有名なセリフがサンプリングされていますが、一方、「Afro Spice」のイントロのギターリフはジミヘンオマージュ的な音の感触です。これは意識されてそうされたのでしょうか?
 A1: サンプリングネタバレましたか(笑)。Jimi の作品の中で「AXIS:Bold As Love」がダントツで好きです。確かに「Afro Spice」のリフはロックフィールですが、これはロックあがりの自分としては自然と出てきたリフです。Jimi へのオマージュとしてはむしろ「AXIS:Bold As Love」の一曲目「EXP」で聴かれる、バイクの音を模したサイケデリックなギターの感じを「Blind Street」の後半に入れました。
A1: サンプリングネタバレましたか(笑)。Jimi の作品の中で「AXIS:Bold As Love」がダントツで好きです。確かに「Afro Spice」のリフはロックフィールですが、これはロックあがりの自分としては自然と出てきたリフです。Jimi へのオマージュとしてはむしろ「AXIS:Bold As Love」の一曲目「EXP」で聴かれる、バイクの音を模したサイケデリックなギターの感じを「Blind Street」の後半に入れました。
 Q2: 「Interlude 2」など一部の曲を除いて、全体の音の感触というかマスタリングの傾向として、全楽器がディストーション多めになっている印象があるのですが、これはどういった狙いがあるのでしょうか?
Q2: 「Interlude 2」など一部の曲を除いて、全体の音の感触というかマスタリングの傾向として、全楽器がディストーション多めになっている印象があるのですが、これはどういった狙いがあるのでしょうか?
 A2: 根本的に録音した場所が福生のカフェで、ガレージ感を出したかったんです。高級スタジオの様なクリーンな音ではないんですが、その方がFUNKかなと。それでマスタリングの際にはビンテージ機材をふんだんに使って Booker T みたいなメンフィスサウンドを意識して音作りをしました。
A2: 根本的に録音した場所が福生のカフェで、ガレージ感を出したかったんです。高級スタジオの様なクリーンな音ではないんですが、その方がFUNKかなと。それでマスタリングの際にはビンテージ機材をふんだんに使って Booker T みたいなメンフィスサウンドを意識して音作りをしました。
 Q3: ファンクっぽさ、ハードロックっぽさ、ヒップホップぽさ、ハードボッサぽさなど、さまざまなジャンルが自然にブレンドされ血肉と化して、素晴らしくオリジナルな音楽とサウンドになっているという印象を受けましたが、ご自身ではいちばんの軸足はどのジャンルにあるとお考えでしょうか?(ジャンル分けというものが本質的には意味がないことは承知の上で)
Q3: ファンクっぽさ、ハードロックっぽさ、ヒップホップぽさ、ハードボッサぽさなど、さまざまなジャンルが自然にブレンドされ血肉と化して、素晴らしくオリジナルな音楽とサウンドになっているという印象を受けましたが、ご自身ではいちばんの軸足はどのジャンルにあるとお考えでしょうか?(ジャンル分けというものが本質的には意味がないことは承知の上で)
あるいは、もし「ジャンル」でないとしたら、ご自身の(トリオジャズ、今回の Speaker Sgt. などさまざまなフォーマットに共通して)最も大事にしているエレメントをひとことでいうとどういったものになりますでしょうか?
 A3: おっしゃる通りそれら全ての音楽が自分の血肉です(笑)。
A3: おっしゃる通りそれら全ての音楽が自分の血肉です(笑)。
バンドのサウンドをジャンルに当てはめるのは正直難しいと思います。ジャズファンク、グルーヴジャズになるんでしょうが何れにせよイギリス的な発想ですよね。敢えて言うなら、それこそタワレコのバイヤーの方がつけてくれた「オトナファンク」「アダルトファンク」ですかね。
自分自身の活動ではジャズがメインです。ジャズと言っても、単なるフォームとしてのジャズではなく、Great African-American Classical Art Form としてアメリカンミュージックの一つ、と捉えています。ブラックミュージックも、ロックも、カントリーも、アメリカで生まれた音楽は、僕は同胞の様に感じます。それは、リズムパターンや歌詞や地方や諸々が違えど、アメリカという懐の深さが生み出した文化であって芸術なわけです。自分はその様な視点で音楽を捉えているので、自分からこれは何だと言われれば「アメリカンミュージック」としか言いようがないかもしれません。
なので、このバンドにしても、自分が作る音楽の大事な要素としてモノマネでない事、本質をしっかり理解しリスペクトしたうえでステイツの連中と張り合えるクオリティとアイディアとオリジナリティが必要不可欠だと思います。もっと簡単に本質的な事を言うと、音符を出すポイントです。それさえ理解していればたった一音でジャック・ディジョネットとスティーブ・ジョーダンと音楽で会話できると思います。これが一番大事かな? だって、これだけはいくら金払っても絶対学校で教えてもらえないですからね(笑)。
 Q4: ほぼ全ての曲で越智さんがクレジットされていますが、Jazzlife インタビューの通り、越智さんが各曲のアイデアを持ってきて、それを3人で肉付けしていく感じでの共同作業だったのでしょうか?それ以外のパターン(他のメンバーの方が最初にアイデアを持ってきたなど)はありましたでしょうか?あったとしたらどの曲でしょうか?
Q4: ほぼ全ての曲で越智さんがクレジットされていますが、Jazzlife インタビューの通り、越智さんが各曲のアイデアを持ってきて、それを3人で肉付けしていく感じでの共同作業だったのでしょうか?それ以外のパターン(他のメンバーの方が最初にアイデアを持ってきたなど)はありましたでしょうか?あったとしたらどの曲でしょうか?
 A4: 基本的に自分が譜面に起こして持っていったものを、メンバーなりの解釈で仕上げていきます。丸投げです(笑)。敢えてそうしてます。このメンバーで出せる音が Speaker Sgt. そのものなので。
A4: 基本的に自分が譜面に起こして持っていったものを、メンバーなりの解釈で仕上げていきます。丸投げです(笑)。敢えてそうしてます。このメンバーで出せる音が Speaker Sgt. そのものなので。
今作の「Chestnut Head」は、珍しく梅沢がコード進行だけ持ってきて、それに自分がメロディを乗せました。
 Q5: 1st アルバムは「いかにも(当時の)ジャズファンクっぽいテイストをたたえたヒップホップ」(もちろんこれは褒め言葉です笑)でしたが、本アルバムでは、明らかに重量系ファンク(しかも音の感触はハードロックぽくもあり、ソロは素晴らしくジャジー)へと軸足が移っているように感じました。これは、2nd アルバム以降、メンバーチェンジがあり、長らくロードで煮詰めていったことの影響でしょうか?
Q5: 1st アルバムは「いかにも(当時の)ジャズファンクっぽいテイストをたたえたヒップホップ」(もちろんこれは褒め言葉です笑)でしたが、本アルバムでは、明らかに重量系ファンク(しかも音の感触はハードロックぽくもあり、ソロは素晴らしくジャジー)へと軸足が移っているように感じました。これは、2nd アルバム以降、メンバーチェンジがあり、長らくロードで煮詰めていったことの影響でしょうか?
 A5: メンバーチェンジによるところは大きいですね。一発録りのファンク系は、よりライブ感、躍動感を打ち出していこう、と思いました。同時に、ヒップホップトラックも入れる事で、作品的に面白いものにしたいなと。
A5: メンバーチェンジによるところは大きいですね。一発録りのファンク系は、よりライブ感、躍動感を打ち出していこう、と思いました。同時に、ヒップホップトラックも入れる事で、作品的に面白いものにしたいなと。
 Q6: Eddie が数曲オルガンで参加していますが、セッションの時の様子を(差し支えない範囲内で結構ですので)教えてください。彼にどのように弾いてほしいと伝えたのか、どのようにアレンジを煮詰め共有していったのか、など。
Q6: Eddie が数曲オルガンで参加していますが、セッションの時の様子を(差し支えない範囲内で結構ですので)教えてください。彼にどのように弾いてほしいと伝えたのか、どのようにアレンジを煮詰め共有していったのか、など。
 A6: オルガンはオーバーダブでしたが、Eddie には曲ごとに割と事細かく注文しました。でも彼は、バンドのサウンドをすぐに理解してくれて、ほとんどワンテイクかツーテイクで済んだので、流石だなと思いました。
A6: オルガンはオーバーダブでしたが、Eddie には曲ごとに割と事細かく注文しました。でも彼は、バンドのサウンドをすぐに理解してくれて、ほとんどワンテイクかツーテイクで済んだので、流石だなと思いました。
 Q7: 越智さん(と、可能であれば梅沢さん、佐藤さんも)の最も敬愛するアーティスト、あるいはアルバムについて聞かせてください。1人(あるいは1枚)に絞るのが難しければ、複数でももちろん構いません(笑)
Q7: 越智さん(と、可能であれば梅沢さん、佐藤さんも)の最も敬愛するアーティスト、あるいはアルバムについて聞かせてください。1人(あるいは1枚)に絞るのが難しければ、複数でももちろん構いません(笑)
 A7: アーティストは沢山いすぎるのでアルバムで。
A7: アーティストは沢山いすぎるのでアルバムで。
越智:Innervisions / Stevie Wonder
梅沢:Joshua Tree / U2
佐藤:By Numbers / The Who