昔懐かし、蓄音機でかける、割れやすいレコード。
10インチ (片面3分程度) / 12インチ (片面5分程度) が一般的です。
回転数は、当初は 80rpm、76rpm など、いろいろあったようですが、のちに 78rpm に統一されました(正確には 78.26rpm)。
で、そのレコードを指して、日本では SP盤 と呼ばれることが多いです。いわく、LP盤 (33 1/3rpm の Long Playing) に対して、Standard Playing の省略形である、と。
しかし、不思議なのです。日本以外で「SP」や「Standard Playing」という表記を見かけたことがありません。 代わりに英語圏でよく見かけるのは「78rpm」「Shellac Records」「Phonograph Records」「Gramophone Records」といったものばかり。
どうして、日本だけ別の呼び方になったのか、あるいは他の国でも「SP」という表記があるのか、なんとなく気になったので、いろいろ調べてみました。もともとは Twitter 上でのつぶやきから始まったものですが、ここにまとめておきます。
(主に)78回転の古いレコードのことを「SP盤」と言い、そのSPが "Standard Playing" の省略形である、というのは、日本独自の文化であって、欧米では全く通用しない(通常 "78rpm" とか "Shellac Records" という)、と思っているのですが、その辺をもう少し掘ってみました。
— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) June 13, 2022
Contents / 目次
英語圏ではなんと呼ばれているか
78rpm records
もっとも多く目にする表現は、そのまま 78rpm、つまり回転数での表現です。
- 78rpms
- 78rpm records
- 78rpm discs/disks
実際には、最初期には 80rpm、76rpm、その他いろんな回転数がレーベル毎に存在した時期がありました。また、同一レーベルであっても、必ずしも回転数が一定ではない時期もあったりしました。1912年に業界標準として 78rpm に統一されましたが、実際に全てのレコードが 78rpm に揃うのは1930年代に入ってからだそうです。
shellac records
次いで目にするのは shellac records、つまり材質での表現です。ちょうど、現在のLPレコードなどのことを vinyl records と呼ぶのと似ていますね。
SP盤末期には、LPなどと同様のポリ塩化ヴィニール製のものもありましたが、1896年に市販開始された時から50年近く、ラックカイガラムシの分泌液から作られた天然樹脂(シェラック)を主成分として作られていたので、「昔のレコード」というニュアンスの表現として、昔の材質を使った呼称になるのもまた理解できます。
Gramophone / Phonograph records
その他にも、Gramophone records (グラモフォン) や Phonograph records (フォノグラフ) という表現もよく目にします。日本で言う「蓄音機レコード」的な(「昔の」というニュアンスの)表現ですね。
厳密には、Gramophone はエミール・ベルリナー (Emile Berliner) が特許を取得、製品化した7インチの円盤レコードと再生装置を指します。
同様に、Phonograph はトーマス・エジソン (Thomas Edison) が特許を取得、製品化した蝋管レコードと再生装置を指します。
widegroove
音溝の太さ由来の、あまり一般的には見ない表現ですが、1950年代に GE (General Electric) が出していた、VR (Variable Reluctance) というカートリッジの取扱説明書には wide groove という表記が見られます。これは、新しいレコード(LP/シングル盤/EPなど)の細い溝 (microgroove) をトレースするのが 1mil の針 (のちに 0.7milに) であり、従来のレコードは、それよりも溝の幅が広い (wide groove) ために 3mil または 2.5mil の針で再生する、ってことを表しているわけですね。特に VR カートリッジは、SP用とLP用の2つの針がついていて、レバーで切り替えられるようになっていたので、なおさら「間違った針で再生しないで」という注意喚起も兼ねていたと推測されます。
針の方では、General Electric VR(日本では「バリレラ」)カートリッジのカタログには "microgroove" に対して "wide groove" となってます。前者が 1mil(のちに0.7mil)、後者が 3mil です。GE のみの呼称かどうかは不明です。"Long Playing Microgroove" はレーベルによく登場しますが。 https://t.co/Ak9W1XHMUd pic.twitter.com/lh4mEOvR1K
— Kohji Matsubayashi (@kohji405mi16) June 14, 2022
Coarse groove
同じく音溝の太さ由来の表現ですが、欧米の規格文書で “Coarse groove disc” “Fine groove disc” という表現がよく見られるそうです。Twitter 上で教えてくださった serieril (せりえりる) さん、ありがとうございます。
これはLPが出た後の言葉だけれど、SP=Coarse groove disc, LP=Fine groove disc, (Columbiaの売り文句で)Micro groove discって書いてあるのを見る。LPが出る前は、SPのことは単にDiscと書いてある。 https://t.co/X2SjymVjtA
— serieril(せりえりる) (@serieril) June 14, 2022
しかし、英語圏で「SP disc」または「Standard Playing records」といった表記をみかけることは全くありません。
近隣の国ではなんと呼ばれているか
韓国: 표준시간 음반
お隣の韓国では “표준시간 음반” と呼ぶそうです。日本語にすると「標準時間音盤」、つまり Standard Playing Record、SP盤ですね。やはり日本や日本語の影響が大きかったのでしょうか。
中国: 胶木唱片
一方、中国では “胶木唱片” と呼ぶそうです。日本語にすると「ベークライトレコード」、つまり、”Shellac Records” に近いってことですね。一方、以下の百度のページでは「SP, Standard Playing」という表記もあわせて見られます。やはり日本や日本語の影響でしょうか。
The Billboard 誌にみる、アメリカでの表記の変遷
そこで、以前 EP (Extended Playing) 盤の歴史というか本来の意味を調べた際に行ったように、新しいメディア LP (Long Playing Microgroove) レコード登場直後の The Billboard 誌を調べてみることにしました。
一般のリスナーが読む雑誌/新聞であったのと同時に、業界誌としての役割もありましたし、新しいメディア (LP) が登場した際に、従来のメディア (SP) のことをどう表現していったか、その変遷を追えるかも、と思ったからです。
The Billboard, June 5, 1948, p.17
以前も引用したこの記事、ちょうど Columbia が初めて 33 1/3 rpm の新メディア「LP」を発表した直後あたりのもので、”long-playing” や “micro-groove” といった単語のおそらく初出と思われますが、この記事の中では、従来のレコード (SP盤) のことは “regular disk” であったり “orthodox 10-inch disk” と表現されています。
The Billboard, December 4, 1948, p.21
こちらは半年後の記事です。Columbia の Long Playing Microgroove Record (LP) に対抗して RCA Victor が発表した、45 rpm の新メディアについて触れられていますが、ここでは “standard 78 r.p.m. records” や “regular 78 r.p.m. records” と表現されています。
The Billboard, February 12, 1949, p.16
Columbia (33 1/3) 対 RCA Victor (45) の仁義なき戦いが激しさを増す中、1949年2月に Capitol が 45 rpm 陣営に参画を表明します。この時の記事ですが、”regular 78 r.p.m. releases” や、その省略形であろう “78 disks” といった表現が見られます。
The Billboard, July 23, 1949, p.17
Capitol が3種類のスピード (33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm) 全てに対応することを表明した記事です。このあたりまでくると “regular 78 r.p.m.” という表記が徐々に減り、シンプルに “78 r.p.m.” のみで書かれることが増えているようです。
The Billboard, April 22, 1950, p.23
そして、RCA Victor がついに 33 1/3 rpm のリリース、つまり3スピード対応を表明した時の記事です。ここでは “standard 78 r.p.m.” という表記の他に “old 78 r.p.m.” なんていう表現も目に入ります。
The Billboard, July 15, 1950, p.3
最後に、Columbia (33 1/3) 側についていた、当時のアメリカ3大メジャーレーベル(Columbia, RCA Victor, Decca) の残り1社である Decca が 45 rpm のリリースを表明し、同じく3スピード対応を発表した記事です。
これにより、Columbia (33 1/3) vs RCA Victor (45) による新フォーマット戦争は終結し、全フォーマットが棲み分ける市場が確定します。
この記事においては、更に短縮して、単純に “33 1/3” “45” “78” と表記されています。
推測:なぜ米国では「78 rpm」という表現が一般的なのか
ここまで Billboard 誌面で追ってきたように、Columbia と RCA Victor の新フォーマット戦争は、回転スピードで比較されることとなりました。
Columbia は 33 1/3 rpm の 7インチ/10インチ/12インチ、マイクログルーヴ。
RCA Victor は 45 rpm の 7インチ、マイクログルーヴ。
このことから、「33 1/3」と「45」が、それぞれの新フォーマットの代名詞となったわけです。結果、従来のレコードについては、それと対比するために「78」が使われるようになった、と。
つまり、英語圏で「78rpm」と呼ばれることが多いのは、1949〜1951年のドタバタがあったから、ということなんでしょうね。
推測:なぜ日本では「SP盤」という独自表現が生まれたのか
前述の通り、アメリカでは1949年に 33 1/3 rpm と 45 rpm が登場、激しい主導権争いののち、1951年に3スピード棲み分けで集結します。
では、日本ではどうだったのでしょうか。
いろいろ調べてみると、日本で初めてLPレコード (33 1/3 rpm) が販売開始されたのは1951年のことだそうです。また、いわゆる シングル盤 (45 rpm) が日本に導入されたのは1954年とのことです。
つまり、日本においては、Columbia vs RCA Victor のスピードバトルのようなことは起こっていなかったということになります。
だから、
- 従来の(蓄音機や電蓄でかける)レコードの代わりとなる、新しいレコードが1951年に登場した
- → それは「LP = Long Playing」レコードと呼ばれているらしい
- → では、今までのレコードはなんと表現したらいいか → じゃあ「SP = Standard Playing または Short Playing」にしよう
と、日本独自表現を生むこととなったのかもしれませんね。
特に物的証拠のない推測ではありますが、意外とあたってる気はしています。けれども、このあたりの具体的な経緯については、国立国会図書館に行って、当時の音楽雑誌、業界誌、オーディオ誌などを調査する必要があるとも考えます。いつかやってみたいなぁ。
今回触れた「SP盤」という日本独自表現の経緯について、なにか知見をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
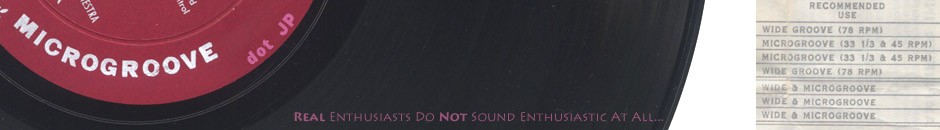



すごく面白い記事でした!関係ないですが最近はCDでも収録曲が少ない、特別版のようなものをEPと称して発売していることがありますね。何かよくわらないけどカッコイイ感があります(笑)
あちらのコメントにも反応していただきありがとうございます(笑)
別記事で書いた通り、「EP」の本来の意味は
* 45回転7インチシングル盤と形状や回転数は同じ
* シングル盤よりカッティングレベルを下げることで単位当たりの記録密度をあげ、
* かつシングル盤よりもっと内側まで記録することで、
* 片面あたり8分程度記録可能にしたメディア
ということになりますね。1952年に RCA Victor が出したのが最初です。
その EP が、時代を経て、12インチ45回転盤で片面2曲以上収録したものであったり、通常サイズのCDで通常より収録曲が少ないがミニCD(CDシングル)ではないものであったり、に対しても EP という呼称が転用された、ということになるかと。
ところで「Uniquities」リリース、本当に楽しみですね。
詳細ありがとうございます!
しばらく見てなくて失礼いたしました
たのしみですね!
LPはビニール盤のことであれば、SPは実はドイツ語のSchellackplatteの短縮で材料についての名称ではないか!? と思いついてドイツ語サイトを検索しまくりましたが、SchellackplatteとSPという言葉が関連付いて出て来るサイトはオーディオテクニカ始め日本製の針絡みばかりで、全く見当外れっぽいです :-)。やはりStandard Play の短縮形、等が正しいのでしょうね。ちなみにドイツ人がレコードをSPと呼んでいるのは個人売買サイトで45rpmのシングル盤のことをSPと称している一例のみでした。そういう呼び方も一部ではされている、のかもしれません。
ドイツ語で Schellackplatte と言うのは知りませんでした。
https://de.wikipedia.org/wiki/Schellackplatte
Wikipedia のエントリ、特に各言語版へのリンクを見ると、ほとんどの国が「78」と回転数による呼称となっていて、ドイツ語では素材による呼称「シェラック盤」なんですね。
日本では(LP登場前は)「チコンキ盤」(「蓄音機」の崩し)と呼ばれていたように思いますが、それは米英での「Phonograph Record」と同等の、再生機器による呼称ですね。
やはり日本での「SP」という呼び方は、「LP」が登場したあとだから、それに対比させる意味合いがあったんじゃないかなぁ、と思っています。
最後は国立国会図書館を漁っていくしかないんでしょうね(笑)