Category: Audio
Refugee 氏宅訪問
で昨日は車を走らせて Refugee さん のお宅に遊びに行ったのですが。
本当は Re-Equalizer とか フォノイコとか持っていく予定だったのですが、出発直前の大雨と雷にて急遽中止、 カートリッジ2個と LP と SP だけ車に載せていざ出発。
行きは環八も東名高速も混んでおらず、予想外に早く到着。 帰りは環八大渋滞で、行きより1時間も余計にかかってしまったのですが . . .
Continue readingThe Firebird / London Symphony, Dorati
(本エントリは、私が別の web に 2004年 6月 23日付で掲載していたものを転載後加筆訂正したものです) (this article is an impression of my surprise meet with the great-sounding LP, Firebird / LSO, Dorati, left on Mercury label. and it was originally made public at my another web site on June 23, 2004. English version of this article (probably) will not be available.)
“The Golden Age of Recording” (Michael Gray、嶋 護 翻訳) より:
もっとも完璧なレコードを選ぶコンテストがあったら、この一枚を推しよう。
2002年頃、この一文で始まる記事を某雑誌で初めて読んだ時、「またそんなおおげさな」と思ったものです。
しかし、実際にその盤を聴いてみた時、ぐうの音も出ませんでした。超絶な録音、スリリングな演奏、その両方の素晴らしさに、本当に鳥肌をたてながらスピーカの前で呆然としてしまいました。これはマジでとんでもないレコードでした。うちの現状のオーディオではその半分、いや二割も享受できていないのかもしれませんが。
Continue readingWanna See My (Poor) LP Stockers?
… this article is totally nonsense – bringing disgrace on myself by showing my own record stockers …
新春自爆企画 レコード棚を曝そう ですって。 Parlophone さん とか MASA さん とか 路傍の石 さん のところとか。
なにやら面白そうなので私も参加させてもらうことにしましょう (笑) 2006年 1月 7日現在のうちの収納状況。
はぁ、もっと広い家に引っ越したいのう。
Continue readingSME 3009R ラテラルバランス調整
秋です。音楽の秋です。
うちでは夏にエアコンを滅多に使わないので、真空管が熱くなるその季節には (部屋が尋常ではなく暑くなってしまい) 自然とアンプに火を入れる機会が減ってしまうのです。また、賃貸マンションである現住居では、エアコンとオーディオのブレーカーが共通で、エアコン使用時にはフォノイコライザアンプが盛大にノイズを拾ってしまうのも一因です。
Continue reading季刊 analog Vol.8
この前出た analog vol.8 の表紙に、見慣れたプレーヤーが登場。
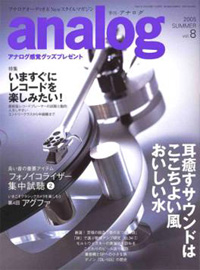
久しく日本で最新モデルが販売されていなかった、私が現在使っているプレーヤー J.A. Michell Gyrodec の最新モデル (Mk.V) が、再び国内で正規販売されることになったようで。 私が使っているのは 1993年モデル (Mk.III) の中古ですが。
しかし、この内外の価格差はどうにかならんのか。 GyroSE RB-300 付が 409,500円 (アメリカだと $2,550)… ローエンドモデルの TechnoDec ですら国内価格が 273,000円というのはかなり割高な様な (同じく $1,695 USD) …
記事の通り、セッティングはとても微妙で大変だけど、それに見合う素晴らしい再生を実現してくれますし、(欧米価格を基準に考えると) とてもハイC/Pなターンテーブルで、日本でも是非もっとユーザが増えて欲しいと思うのですが、この値段は微妙ですな。
今日ト云フ日ヲ忘レナイ
今日は仕事で恵比寿へ。帰りに新宿で途中下車。 準備万端のプレーヤー のために、SP 用カートリッジを買って帰る。結局安い AT-MONO3/SP にした。
Continue reading七十八回轉準備完了
私が 2003年9月 より愛用している現在のターンテーブル J.A. Michell Gyrodec Mk. III (with plinth-based Papst AC motor driven by GyroPower QC)。このターンテーブル用の 78rpm プーリーがかつて存在していたという噂を耳にし、英国 J.A. Michell 本社に問い合わせをしましたが、「倉庫に残ってるかもしれん。気長に待っとくれ」という返事を最後に数ヶ月音沙汰なし。ダメもとでアメリカのショップに問い合わせをしたら、在庫ありとのことで早速注文。ものはついでと、予備のゴムベルトも同時発注。で、本日届きました。50Hz 用 33/45/78 回転用プーリーとゴムベルト。

写真の銀色のプーリーがそれ。3つ溝が切られていて、上から 33 1/3 回転、45回転、78回転用となっています。左にぽつんと置いてある黒い方は、直前まで使っていたプーリー。こちらは 2ベルト駆動対応版 (Mk.II あたりまでは純正で 2ベルト駆動だった名残りでしょうか) で、上から 45回転、33 1/3回転、33 1/3 回転、45回転と溝が切られています。
あとはカートリッジさえ買えば、うちでもめでたく SP 盤が再生可能になります。ここはいっちょ Ortofon CG65Di を、と言いたいところですが、クルマのメンテにお金がかかることを鑑み Audio Technica AT-MONO3/SP あたりが無難か。
Continue reading耳ヲ奪ハルル
![[Zu Druid Mk4]](https://microgroove.jp/shaolin/img/Zu_Druid.jpg)
月曜日、仕事で出て行った帰りに某オーディオショップに立ち寄り、あれやこれや物色したりして、さあ帰ろうかとエレベータを待っている時に、後ろから物凄い音の誘惑が。
ふわ〜っっと広がった清涼な空気感、嫌味なく優しく澄み切った音色、しかして芯に力強さのある音。透き通ってるのに前に出てくる音。
(どちらかというと僕の好みではない) 透明感溢れる音場感最優先の現代的スピーカーとはやや違う。けど今うちで使っている様な若気の至りガンガンな音というわけでもない。その両者のいいとこどりというか、透き通りつつ力強い、なによりシビれる程に心地よい音。
なんじゃこりゃ。と、その奏でる音に心を奪われている間に、エレベータの扉は開き、閉じてしまっていました。
で、小出力の真空管プリメインを介して SACD の音を奏でていたそのスピーカーは Zu Druid Mk4 という聞き慣れないアメリカ製でした。よくわかんないけど正規輸入されてないのかな。今どき奇跡的な 101dB という超高能率といい、その端整なルックスといい、出てくる音の自分の好みとの近さといい、一発で虜になってしまいました。
僕が金持ちやったら迷うことなくその場で買うてたね。無理やけど。
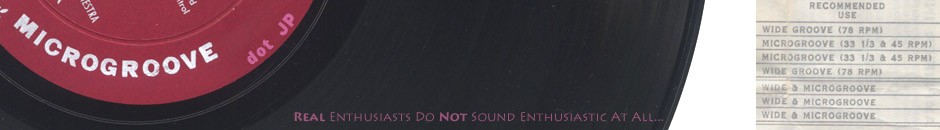
![[Command Performance]](https://microgroove.jp/img/CommandP1942_00030000.jpg)
![[Sound And The Story]](https://microgroove.jp/img/SoundAndTheS_00133000.jpg)
![[ESOTERIC SOUND RE-EQUALIZER]](https://microgroove.jp/img/IMG_2102-L.jpg)