Feb. 28, 2004: Jam Session Night at Eddie’s Lounge
![[Eddie's Lounge]](/shaolin/img/EddiesLounge.png)
Here I come again. It’s been several months since I visited Eddie-chan’s lounge located at Kitasenju last (when his lounge was a grand opening day).
To tell the truth, at that time I thought and was afraid whether he would/could have constant visitors after the grand opening day was over, but fortunately it was definitely needless worries.
北千住の Eddie ちゃんのお店に行くのはオープン初日以来ということになります.オープン当時は「これからコンスタントにお客さん入ってくれるのかしら」と若干心配していましたが,杞憂に終わった様です.
After the grand opening day, he had tried several attempts: placing a tiny drum set in the tiny lounge, digging jam sessions every Saturday night. I am so glad to see he has been enlarging his local, friendly and invaluable community.
その後小さめのドラムセットを設置したり,毎週土曜日には自由参加可能なジャムセッションを開いたりと,Eddie ちゃんのいろんな試みが実ってか,着実に草の根コミュニティは拡がりつつある様でほっと一安心.
![[Jam Session with Eddie Landsberg at Eddie's Lounge]](/shaolin/img/2004.02.28.EddiesLounge/DCP_0076.jpg)
Yesterday Saturday night, I went to Eddie-chan’s lounge with Hatta-san, who wished to join the jam (but couldn’t, as he couldn’t prepare an amplified pianica/melodica till yesterday night). Two altos (one also played organ, the other also on drums), one tenor, two guitars, one drums, as well as a nice lady who played duet organ performance with Eddie-san, were the members who joined to the jam led by Mr. Eddie Landsberg (who also played drums). Anyway it was again an enjoyable and comfortable night. Thanks Eddie-chan.
で,昨晩は,ジャムセッションに参加したいと言っていた 八田さん と共に訪れました.残念ながら,ピアニカの調達が間に合わず,八田さんの演奏への参加はかないませんでしたが.alto sax 2名 (うち 1名は organ も,もう 1名は drums も),tenor sax 1名, guitar 2名, drums 1名, Eddie ちゃんと連弾で飛び入りの 1名,そして Eddie ちゃん (drums も披露) でわいわいとジャムが行われました.ともあれ,昨晩もとても楽しい夜を過ごす事ができました.エディーちゃんありがとう.
Another fortunate was that I could watch the complete version of the legendary James Brown performance at Dallas in 1968 (just after Martin Luther King was assassinated).
もう 1つ嬉しかったのは,あの1968年ダラスでの JB のライブ (Martin Luther King 暗殺直後) の完全版ビデオを観ることができたことでした 🙂
…and finally here are some of the photos I took yesterday night…
というわけで昨晩の写真をいくつか:
Continue reading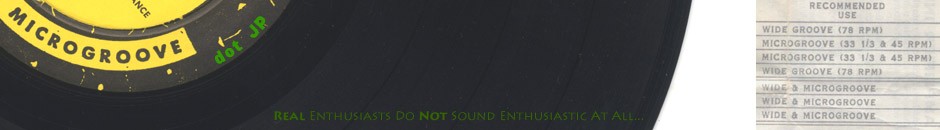
![[Jam Session with Eddie Landsberg at Eddie's Lounge]](/shaolin/img/2004.02.28.EddiesLounge/DCP_0060.jpg)
![[Phonomena + BPS]](https://microgroove.jp/shaolin/img/Phonomena2.jpg)
![[JAN Sylvania 6SN7WGT]](https://microgroove.jp/shaolin/img/6SN7WGT-L.jpg)
![[Phonomena]](https://microgroove.jp/shaolin/img/Phonomena.jpg)
![[Eddie Landsberg]](/shaolin/img/20031026-EddiesLounge-1.jpg)
![[Eddie Landsberg]](/shaolin/img/20031026-EddiesLounge-2.jpg)
![[GyroPower QC]](https://microgroove.jp/shaolin/img/GyroPowerQC-L.jpg)