R.I.P., Mr. Duke Jordan
享年84歳。コペンハーゲンにて息を引き取られたそうです。 Pianist Duke Jordan dead at age 84 (United Press International) RIP Duke Jordan, 1922-2006 (Blogcritics.org)…
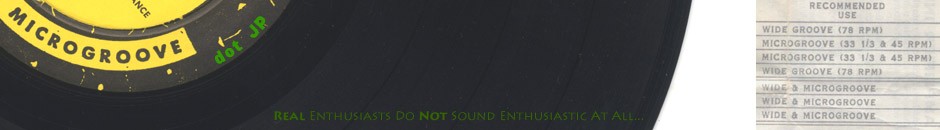
享年84歳。コペンハーゲンにて息を引き取られたそうです。 Pianist Duke Jordan dead at age 84 (United Press International) RIP Duke Jordan, 1922-2006 (Blogcritics.org)…
Volkswagen Type II 型のレコードプレーヤガジェット、確実にレコードを痛めそうですが(笑)とにかく楽しいです。うちにあるのは1970〜80年代製の「Record Runner MUSIC’N」ですが、「ちょろっこ」「Vinyl Killer」「Soundwagon」さまざまな名前で販売されています。
ELENCO レーベルの3枚目 ME-3 は、ホベルト・メネスカル (Roberto Menescal) の快速ボッサアルバム。さわやかさを通り越して「夏だ!海だ!」感満載、ボッサ・ノーヴァの「陽」を極限まで引き出しています。
私が好きなタイプの音楽が多くラインアップされている、ドイツの MORR Music レーベルから 2005年2月にリリースされたアルバム。昨年暮れに購入してから、最近徐々にターンテーブルに載せる頻度があがってきました。CD と共に LP でも同時リリースされており、こちらは 2枚組 (1枚目が33 1/3回転、2枚目が45回転という変則な組合せ)。もちろん迷うことなく後者を購入しました。 This album, released in February 2005 from German label MORR Music (whose catalogue contains many titles I like), was the one I bought last year. Recently I often…
昨日、自宅にて某雑誌の取材を受けました。若いビジネスマン向け?の一般?雑誌で、音楽雑誌でもなく (そらそうだ) オーディオ雑誌でもなく (そらそうだ)。果たしてどんな切り口や視点 (あるいはバイアス) からの取材なのか、当初は一抹の不安もあったのですが、終わってみればとても楽しい二時間でした。
Monk’s Music / Thelonious Monk (Riverside [US] RLP-1102) (stereo 2nd cover, Orpheum turquoise label) はじめに (愛すべきハッタリステレオとの出会い) 誰もが知ってる Monk’s Music。演奏破綻寸前のカオス状態が逆にえもいわれぬ迫力を生み出しているという、不思議な魅力に満ちた傑作です。1957年 6月 25〜26日録音。 上に載せたのは ステレオ盤 (の後期プレス、いわゆる Orpheum 盤)。大学入学直後、まだジャズを聴きだしたばかりの私が、大阪梅田の某中古レコード屋で確か 1,800円で買ったものです。私が買ったモンクのアルバムとしても 2枚目 (*1) でした。すでにその頃、初心者には嬉しい OJC なる LP リイシューの存在も知っていましたが、ジャケットを見る限り OJC の方はモノーラル。たまたまステレオ盤の中古を安く見付けたのでそちらを買ったというわけです。ですから、私にとっては長らく、“Monk’s Music” といえば、このハチャメチャっぷりが更に増幅された音が楽しめるステレオ盤を意味していました。ステレオ盤に入っていない B面ラストの…
先日、mhatta さんに 教えてもらって 速攻で購入した CD。 なんといっても Monk と Steve Lacy の共演が聴ける (!!) というだけでそそられます。 The other day mhatta-san let me know the release of the CD – we can finally listen to the Monk quartet with Steve Lacy on soprano…
突然ですが、ミュージシャンで「Hank なにがし」といえば、誰の名前を思い付きますか? 私が最初に思い付いたのは . . ….
直流点火回路のダイオードの不良による修理から帰ってきたアンプで最初に聴いたのは、Bud Powell の Un Poco Loco、78回転盤です。こ難しい曲と思われることもあるようですが、このテーマ部のラテン風味なアレンジは理屈抜きでカッチョエーとしかいいようがありません。
Charles Mingus の名盤「Tijuana Moods」。このアルバムの2001年版リマスター2CDには、ボーナストラックとしてアルバムに使用されなかったフラグメントが大量に収録されています。実はこのアルバム自体が「アイランド・ホッピング」という手法で録音されたものだったのです。