Things I learned on Phono EQ curves, Pt. 9
第二次大戦中〜戦後のLP登場前夜のさまざまな状況について資料を調べてみました / On Pt.9, I learned on various situations in the US 1940s, until the advent of “microgroove” (fine groove) records.
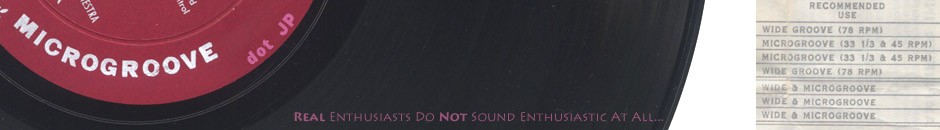
第二次大戦中〜戦後のLP登場前夜のさまざまな状況について資料を調べてみました / On Pt.9, I learned on various situations in the US 1940s, until the advent of “microgroove” (fine groove) records.
1942年「NAB録音・再生標準規格」の策定に至る歴史を学びました / On Pt.8, I learned on the history and background of the formulation of 1942 NAB Standards.
圧電ピックアップの誕生、ジュークボックス、定振幅録音再生の試みなどを学びました / On Pt.7, I learned on piezoelectric pickups, jukeboxes, an attempt of constant-amplitude recording/reproducing etc.
アセテート盤録音機とラッカー盤、高調波歪、軽針圧ピックアップなどを学びました / On Pt.6, I learned on Instantaneous DIsc Recorders and Lacquer discs, Harmonic distortion, Lightweight pickups, etc.
ストコフスキーとベル研、RCA/NBCトランスクリプション、Orthacousticカーブなどを学びました / On Pt.5, I learned on Stokowski=Bell Labs collaboration, RCA/NBC Transcription, and Orthacoustic curve.
Vitaphone とトランスクリプション盤、縦振動トランスクリプションの革新を学びました / On Pt. 4, I learned on Vitaphone, Electrical Transcription, innovation of Bell/WE vertical recording technology.
BlumleinやRCA Victorの録音システムの進歩、マイクの特性などを学びました / On Pt. 3, I learned the history of the development including Blumlein system, RCA Victor system, and microphones.
世界初の電気録音・電蓄、ラジオ業界の脅威について学んでみました / On Pt. 2, I learned more of the history – world’s first electrical recording, first electrical player, and radio craze.
そもそもレコードのEQカーブがなぜ生まれたのか、電気録音黎明期を調べてみました。 / Before digging deeper about EQ curves, I studied why the need for EQ was born at the dawn of Electrical recording.
持論・異論・珍説が飛び交う、議論多き「フォノEQカーブ」について、1920年代電気録音黎明期にまで歴史を遡り、録音・再生カーブのみならずディスク録音全般について正しく理解するために、あらゆる文献、雑誌、論文を調査し学習した軌跡の長編記録です。まずはイントロの「はじめに」から。